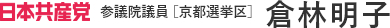年金改定案 撤回求める 参院審議入り / 年金制度改定法案 倉林議員の質問(要旨) 参院本会議(2020/5/15 本会議)
公的年金の受給開始時期の選択肢を75歳まで拡大することなどを盛り込んだ年金制度改定法案が15日の参院本会議で審議入りしました。
日本共産党の倉林明子議員は、新型コロナウイルス感染拡大で働く場が奪われるなど雇用環境が激変していると指摘。必死に雇用を守り事業を継続している中小企業に、厚生年金の適用対象の段階的拡大で新たな保険料負担を求めるタイミングではないと訴え、「コロナ前に検討した改定案は撤回すべきだ」と迫りました。
政府は75歳まで受給開始を遅らせれば月々の年金は84%増えるとしています。倉林氏は、税や保険料の負担も大きく増え、「手取りの年金(総額)は65歳から受給した方がお得だ」と指摘。年金支給水準を自動削減する「マクロ経済スライド」維持が前提で、スライド終了後に75歳から受給した場合、現行の70歳からの受給よりも年金水準(所得代替率)が低くなると追及しました。加藤勝信厚生労働相は75歳からの方が「低くなる」と認めました。
倉林氏は「年金水準が減れば感染リスクが高い高齢者も働き続けなければならなくなる」と強調し、コロナ禍のもと必要なのは年金で安心できる生活を選択できるようにすることだとして、減らない年金への転換のため、マクロ経済スライドの廃止を要求。安倍晋三首相は「廃止は考えていない」と背を向けました。
日本共産党の倉林明子議員が15日の参院本会議で行った、年金制度改定法案についての質問(要旨)は次の通りです。
改定法案では、厚生年金の適用対象とすべき企業の対象を51人以上まで段階的に拡大するとしていますが、これは早期に実施することが求められていました。しかし、やるのは今でしょうか。
新型コロナで、対象となる中小企業の経営環境は激変しています。雇用を守り、事業を継続させている小規模・中小企業に対し、新たに社会保険料負担を求めるというには、最悪のタイミングです。年金制度改定法案は撤回し、提案し直すべきです。
本法案の問題点の第一は、75歳までの繰り下げ受給を選択すれば、本当に得になるのかという点です。
確かに、受給額は1・8倍まで増えるものの、年収が増えれば税や医療・介護の保険料の負担も増加します。
東京都新宿区在住の年金受給者は、85歳までの受給期間で比較した時に、65歳から受給した年金が月15万円なら住民税、所得税の総額は42万円。受給開始を75歳とした場合、受け取る年金は月27・6万円となるものの、負担総額は225万円と5倍を超えます。
つまり、75歳まで受け取りを遅らせた場合、受給額は増えても、手取りの年金は65歳から受給した方が得だということになります。
第二に、本法案は公的年金の水準を自動的に削減するマクロ経済スライドの維持を大前提にしていることです。
この仕組みで、将来の基礎年金水準は3割削減されます。マクロ経済スライド終了後に75歳から年金受け取りを開始した場合の所得代替率は、現在の上限の70歳から受け取った場合よりも低くなるのではありませんか。
受け取れる年金水準が減れば、生活できる収入を確保するために、感染リスクが高い高齢者も働き続けなければなりません。減らない年金制度への転換が必要です。マクロ経済スライドを停止すべきです。最低年金の底上げに踏み出すべきです。
新型コロナ対応として年金生活者支援給付金を抜本的に拡充すべきです。合わせて最低保障年金制度の実現を求めるものです。
第三の問題は、公的年金の削減を進める一方で、リスクを伴う確定拠出年金をさらに推奨していることです。
コロナ経済危機の影響で、今後の株価の推移によっては、投資信託型の確定拠出年金を選択した年金受給者で「元本割れ」「運用利回りがマイナス」になる場合が想定されます。元本保証型を選択している人でも手数料の方が高くなりうるのではありませんか。
安倍政権は、年金積立金の株式運用比率を拡大し続けてきました。今年の4月からは5年半ぶりに基本ポートフォリオを変更し、国内債券を10%減らし、外国債券を15%から25%に増やしています。株式運用比率拡大方針を見直し、リスクを下げる運用に転換すべきです。GPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)が管理する年金積立金の資産構成に占める株式の割合を、まずは20%に戻すべきです。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
私は、日本共産党を代表し、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について質問します。
法案に先立ち、検察庁法改正案について質問します。
法案に抗議する声はSNSで日増しに広がり、日弁連、全国三十八の弁護士会、さらには検事総長経験者など検察OBからも反対の意見が上がっています。
総理は、内閣によって恣意的な人事が行われるという懸念は当たらないと言います。しかし、衆議院内閣委員会で武田担当大臣は、特例的に定年延長を認める際の運用基準は、今はない、今後検討すると述べています。これでは白紙委任せよというようなものです。
法案の強行は許されません。国公法との一括法案から切り離し、定年延長の特例規定を削除する野党の要求を受け入れるべきです。総理、答弁を求めます。
年金法案の大きな改正内容の一つが、これまで七十歳までだった年金受給開始時期の選択肢を七十五歳開始にまで広げることです。その改正の趣旨で、より多くの人が、より長く多様な形で働く社会へと変化する中だと社会を捉えています。
しかし、コロナによって社会は大きく変容しています。雇用環境は激変し、正規雇用以外の多様な働き方をしている人たちが真っ先に首切りや雇い止めに直面しています。働く意欲があっても、働く場所を急速に奪われているのが現実ではありませんか。また、新たな生活様式への行動変容が求められる中、仕事はあっても、感染リスクが高い高齢者が、働き続けることで感染するのではないかとの不安を抱えながら仕事を続けている例も少なくありません。
総理にお聞きします。
コロナによって法改正の前提は大きく変化しているとの認識はありますか。
改正法案では、厚生年金の適用対象とすべき企業の対象を五十一人以上まで段階的に拡大するとしていますが、これまで早期に実施することが求められていたものでした。しかし、やるのは今でしょうか。コロナによって、対象となる中小企業の経営環境は激変しています。必死で雇用を守り、事業を継続させている小規模・中小企業に対し、新たに社会保険料負担を求めるというには、余りにも最悪のタイミングではありませんか。総理、新型コロナが起こる前に検討してきた年金制度改正案は一旦撤回し、改めて提案し直すべきではありませんか。
政府が今やるべきは、新型コロナの対応に全力を尽くすことであり、年金制度についても、いかに年金生活者の生活を支えていくのかという具体的な対応策が求められているのです。
以下、本法案の内容に沿って、問題点を指摘し、見直すべき提案をさせていただきます。
第一に、七十五歳までの繰下げ受給を選択すれば本当にお得になるのかという点です。
確かに、受給額は一・八倍まで増えるものの、年収が増えれば税や医療、介護の保険料の負担も増加します。東京都新宿区在住の年金受給者で見れば、八十五歳までの受給期間で比較したときに、六十五歳から受給した年金が月十五万円なら、住民税、所得税の総額は四十二万円です。受給開始を七十五歳とした場合、受け取る年金は月二十七・六万円となるものの、負担総額は二百二十五万円と五倍を超える負担となることが衆議院の論戦で明らかになりました。つまり、七十五歳まで受取を遅らせた場合、受給額は増えても、手取りの年金は六十五歳から受給した方がお得だということではありませんか。
第二に、本法案は公的年金の水準を自動的に削減するマクロ経済スライドの維持を大前提にしていることです。この仕組みにより、将来の基礎年金の水準は三割も削減されることとなります。マクロ経済スライドが終了した後に七十五歳から年金の受取を開始した場合の所得代替率は、現在の上限である七十歳から受け取った場合よりも低くなるのではありませんか。以上、厚労大臣の答弁を求めます。
受け取れる年金水準が減れば、生活できる収入を確保するために、感染リスクが高い高齢者も働き続けなければならない事態に追い込まれることは明らかです。コロナの下でやるべきは、年金で安心できる生活を選択できるようにすることではありませんか。まずは、減らない年金制度への転換が必要です。マクロ経済スライドを今こそ停止すべきではありませんか。
そもそも、日本の年金水準は国際的に見て決して高い水準とは言えません。OECDの比較にとどまらず、世界的なコンサル会社のマーサーが、二〇〇九年以来、年金制度の国際比較を四十以上の質問項目から構成された評価指数で行っています。そのマーサー・メルボルン・グローバル年金指数ランキングの二〇一九年版によれば、日本の総合指標は三十七か国中三十一位であり、とりわけ十分性での評価が低いと報告されています。国際的に見ても十分な給付レベルが確保できていないことを認めるべきではないでしょうか。
暮らせる年金制度にするために、最低年金の底上げに今こそ踏み出すべきです。新型コロナ対応として年金生活者支援給付金を抜本的に拡充すべきです。あわせて、最低保障年金制度の実現を求めるものです。総理、いかがですか。
底上げのための財源をどう確保するかも問われます。一つは、保険料の能力に応じた応分な負担を求めることです。保険料負担の上限を現在の年収一千万円から二千万円まで引き上げれば、一兆円規模の財源確保が可能です。そして、二〇一九年度末では百七十兆円に達する年金積立金は、今こそ計画的に取り崩して、年金底上げの財源に充てるべきではありませんか。以上四点、総理の答弁を求めます。
本法案の第三の問題は、公的年金の削減を進める一方で、リスクを伴う確定拠出年金を更に推奨するとしていることです。
コロナによる世界的な株安が広がっています。GPIFの運用実績にどんな影響を与えているのか、厚労大臣、二〇二〇年一月から三月の見通しを示していただきたい。
コロナ経済危機の影響で、今後の株価の推移によっては、投資信託型の確定拠出年金を選択した年金受給者で元本割れ、運用利回りがマイナスになる場合が想定されています。元本保証型を選択している人でも、手数料の方が高くなる手数料負けになり得るのではありませんか。その可能性について、厚労大臣の説明を求めるものです。
安倍政権は、年金積立金の株式運用比率を拡大し続けてきました。今年の四月からは五年半ぶりに基本ポートフォリオを変更し、国内債券を一〇%減らし、外国債券を一五%から二五%に増やしています。コロナによる世界同時株安は、株式の運用比率を高めれば高めるほど、国民の財産である年金積立金を大きく毀損させることになることが明らかになったのではありませんか。株式運用比率拡大方針を見直し、リスクを下げる運用に転換すべきです。GPIFが管理する年金積立金の資産構成に占める株式の割合を、まずは二〇%に戻すべきではありませんか。総理の見解を求めます。
新型コロナウイルスは、年金制度のありようにも大きな問題提起をしています。今やるべきは、自動年金引下げ装置となっているマクロ経済スライドを中止し、減らない年金、頼れる年金制度への転換であることを強く求めまして、質問といたします。(拍手)
〔内閣総理大臣安倍晋三君登壇、拍手〕
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 倉林議員にお答えをいたします。
検察官の定年引上げを含む国家公務員法等改正案についてお尋ねがありました。
今般の国家公務員法等の改正法案の趣旨、目的は、高齢期の職員の豊富な知識、経験等を最大限に活用する点などにあるところ、検察庁法の改正部分の趣旨、目的もこれと同じであり、一つの法案として束ねた上で御審議いただくことが適切であると承知しております。
現行の国家公務員法上の勤務延長の要件は改正法において緩和されておらず、また、役職定年制の特例の要件も勤務延長と同様とされており、これらの具体的な要件については、今後、人事院規則において適切に定められるものと承知しております。
その上で、検察官について勤務延長等が認められる要件については、改正後の国家公務員法上の勤務延長等の場合と同様とされており、かつ、これらの具体的な要件は、新たな人事院規則に準じて、あらかじめ内閣府又は法務大臣が定めることとしており、白紙委任との御批判は当たりません。
なお、法案審議のスケジュール等については国会でお決めいただくことであり、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきます。
新型コロナウイルスの発生による年金制度改正案への影響についてお尋ねがありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある御家庭、事業者の方々を徹底的に下支えし、雇用と事業活動、生活を守り抜いていくため、政府としてはあらゆる手だてを講じているところです。
その一方で、我が国において急速に少子高齢化が進み、人生百年時代を迎えようとする中で、全世代型社会保障への改革も待ったなしの状況にあると考えており、年金制度改革においても、働き方の変化を中心に据えて改革を進めることが必要であると考えています。
このため、政府としては、高齢者が意欲を持って働ける環境整備を進めるとともに、そのための手段として、受給開始時期の選択肢を七十五歳まで広げ、受給額についても、年金財政中立の考え方の下、八四%までの割増しを行うことといたしました。
また、被用者保険の適用拡大については、特に、中小企業への影響も大きいことから、関係者の意見を丁寧にお伺いした上で、五十人超の中小企業まで、二〇二二年十月から二〇二四年十月までかけて、段階的に適用範囲を拡大していくこととしております。
こうした改革により支え手を増やし、年金制度全体の安定性を高めることで、低所得の方を含めた将来の年金水準の確保にもつなげていくこととしております。
公的年金制度の給付水準や低年金の方への対応等についてお尋ねがありました。
年金のマクロ経済スライドは、将来世代の給付水準の確保のために不可欠な仕組みであることから、政府として廃止することは考えておりません。また、将来世代に対しても責任ある対応をするためにも、長期的に給付と負担をバランスできる水準を超えて積立金を取り崩し、現在の給付に充当すべきではないと考えています。年金水準の確保については、今回の改正では、被用者保険の適用拡大等を行い、老後の支えとして年金の役割強化を図ることとしているところです。
各国の年金制度を適切に比較するに当たっては、制度内容や保険料率、高齢化率等の前提条件の違いを踏まえる必要があります。御指摘の調査は、海外のコンサルティング会社等が私的年金の評価等にも重点を置いて独自に行ったものであり、こうした前提条件の違いを考慮していないことに加え、評価項目も公的年金制度とは直接関係ない項目が相当程度を占めていると承知しており、公的年金制度を比較する上で必ずしも適当ではないと考えています。
年金生活者支援給付金は、定額給付とした場合は保険料納付のインセンティブを損なうため、社会保険方式になじまないとの観点から、月額五千円を基準としつつ、保険料納付済期間に比例した給付としているものです。さらに、どのような給付を行う場合も、それを支える安定財源がなければ持続可能な制度とならないものと考えます。
最低保障年金については、多額の税財源が必要になり、保険料を払っている方々と払っていない方々との間の公平性をどう担保していくのかといった課題があり、導入は難しいと考えています。
年金積立金の運用についてお尋ねがありました。
年金積立金の運用は、長期的な観点から行うこととされており、株式市場を含む市場の一時的な変動に過度にとらわれるべきではありません。また、年金積立金の運用は、安全かつ効率的に行うことが重要です。このため、経済動向や運用環境などを踏まえて、株式や内外の債券を含めた分散投資により、ポートフォリオ全体としてのリスクを抑えつつ、年金財政上必要な利回りを確保していくことが必要であると考えています。
こうした観点から、GPIFにおいて、専門的な知見に基づき十分に検討を行った上で、被保険者の利益のために最適の資産構成割合が定められたものと考えています。
残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
○国務大臣(加藤勝信君) 倉林明子議員より四問の御質問をいただきました。
繰下げ受給と税、社会保険料の負担についてお尋ねがありました。
公的年金は、終身で受給できることが最大の特徴の一つであります。何歳まで年金を受給することになるかは個々人によって大きく異なるわけであります。また、何歳まで働き、何歳から年金の受給を始めるかについても、個々人が自身の就労状況等に合わせて選んでいただくものであります。
したがって、個々人による選択が様々であることから、一概にどのような選択が得であるかは申し上げられませんが、それぞれの方が御自身にとって適切と思う選択をしていただけるようにしていくことが重要であると考えております。国民の皆さんが自らの就労状況などに合わせて受給開始時期などを適切に選択できるよう、分かりやすい情報提供に努めてまいります。
マクロ経済スライドと繰下げ受給についてお尋ねがありました。
マクロ経済スライドは、将来世代の負担を過重にしないため、保険料水準を固定し、その範囲内で給付水準を徐々に調整する世代間の分かち合いの仕組みであり、現在の受給者も将来の受給者も共に調整されるものであります。また、マクロ経済スライドは、賃金、物価の伸びの範囲内で年金額の伸びを抑えるものであり、実際に支給される名目の年金額そのものが減額されるものではありません。
将来の年金水準を見通す上では、現役期の賃金との比較である所得代替率と年金受給者の購買力を表す物価上昇分を割り戻した実質価格の双方を見ることが大切と考えております。
その上で、そもそも世代が違うということはありますが、あえて比較をしてみると、所得代替率で見た場合、マクロ経済スライドが終了した後に受給者となる世代が七十五歳から受給した水準は、現在受給者となる世代が七十歳から受け取った場合の水準よりも低くなりますが、一方で、購買力を示す実質価格では、二〇一九年の財政検証の代表的なケースでは、六十五歳時点における年金額はマクロ経済スライド調整期間中においてもおおむね横ばいとなっていますので、マクロ経済スライドが終了した後に七十五歳から受給した方が高くなります。
年金積立金の運用実績についてお尋ねがありました。
GPIFの運用状況については、法律に基づきGPIFが業務概況書を作成し、これを公表しなければならないこととされており、年度単位の運用状況の公表を基本としております。一方、四半期ごとの運用状況については、GPIFが中期計画などに基づき自主的な取組として公表しております。
自主運用開始以降の平成十三年度から令和元年度第三・四半期までの収益額の累積は約七十五・二兆円となっていますが、半分程度の約三十六・五兆円は株価下落時でも着実に収益として確保される利子や配当収入等のインカムゲインであり、それ以外の約三十八・七兆円は評価損益などのキャピタルゲインであり、これは時価の変動により上下する性質のものであります。
その上で、GPIFの本年の一月から三月の運用状況については、GPIFにおいて本年七月に昨年度の通期の運用状況を記載した業務概況書において公表することとなっており、それにのっとって公表されるものと承知をしております。
確定拠出年金の運用についてお尋ねがありました。
公的年金に上乗せする確定拠出年金は、拠出、運用、給付において公的年金と同様の税制優遇が認められる制度であります。運用に当たっては、元本確保型を含む様々な運用商品の中から選択することになりますが、長期間にわたって運用を行うものであり、短期的な動向に過度にとらわれるべきものではありません。
また、元本確保型の運用商品を選択した場合、手数料の方が上回る手数料負けになり得るのではないかとの御指摘については、掛金の額、運用商品の利率、受給の回数などによって状況が様々であること、また、拠出、運用、給付時の税制優遇もあることから、一概に申し上げることはできません。
投資教育を担う事業主等への支援などを通じて、加入者が長期的な視点に立って、自身の年齢、資産等の属性に応じた適切な運用の手法を選択できるよう、引き続き取り組んでまいります。