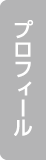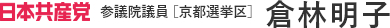訪問介護基本報酬元に戻せ (2025/5/22 厚生労働委員会)
日本共産党の倉林明子議員は22日の参院厚生労働委員会で、介護職員の処遇改善を巡り、2024年度改定で引き下げられた訪問介護の基本報酬を元に戻すなど、3年に1度の報酬改定を待たずに期中改定するよう政府に迫りました。
介護16団体が8日に開催した緊急集会の決議は「現場のあらゆる職員に十分な賃上げができる財源の確保を求める」とし、▽26年度予定の期中改定▽期中改定までの賃上げ補助▽物価高騰や将来の人材確保への支援―を要求しました。倉林氏はこのことを指摘し、「期中改定」を早急に実施すべきだと追及。福岡資麿厚生労働相は「私自身も現場の関係者から切実な要望を聞いている。こうした声もしっかり受け止めたうえで26年度予算編成に臨む」と答えました。
倉林氏は、24年度報酬改定が全体で1・59%のプラスにとどまり、全産業平均の賃上げにほど遠いと批判。「ただちにやるべきは、24年度報酬改定で実施した訪問介護の基本報酬の引き下げを元に戻すという決断だ」と指摘しました。
24年度補正予算の総合対策1103億円のうち、人件費に充てることができる補助金806億円は「常勤職員1人当たり5・4万円の補助で、すずめの涙にもならないとの声が上がっている」と批判。補助対象がすでに職員処遇改善加算を取得している事業所などに限るなどの要件を撤廃するよう要求しました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
五月の八日のことですけれども、介護十六団体が緊急集会を開催されました。賃金格差が月額八万円と拡大する中で、人材流出が加速している実態を示されて、現場のあらゆる職員に十分な賃上げができる財源の確保を求めるとされまして、三点、決議上げられています。一つが、二六年度予定の期中改定、二つ目、期中改定までの賃上げ補助、三つ目が、物価高騰や将来の人材確保への支援ということで上げられているわけです。開会の挨拶に立たれた全国老人保健施設協会会長の東憲太郎会長が、私たちを見捨てないでほしいと、こういう挨拶されたというんですよ。
決議のまず一番目、来年度の期中改定、これ予定しているのか。予定していると聞いていないけれども、これ早急に実施すべきではないかと思いますけれど、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) その緊急集会の内容については承知をしております。御指摘のようにそこの……(発言する者あり)
○委員長(柘植芳文君) 静かにしてください。
○国務大臣(福岡資麿君) 済みません。
緊急集会のことについては承知しています。その中で二〇二六年度予定の期中改定が決議をされたということも承知をしてございます。
介護報酬改定はこれまで原則として三年に一度行ってまいりましたが、令和六年度改定では二年分の処遇改善について措置した上で、三年目の令和八年度の処遇改善については、予算編成過程で検討の上、報酬改定で措置する場合には期中改定で対応することとなります。
御指摘の期中改定につきましては、私自身も現場の関係者の方々から、本当にこのことだけじゃなくて、いろいろな方から切実な御要望をお聞きしております。こうしたお声もしっかり受け止めた上で、令和八年度予算編成に臨ませていただきたいと考えています。
介護職員の処遇改善は喫緊の課題であると認識しておりまして、報酬改定であったり補正予算等によりまして賃上げに対応する措置を講じてきておりまして、これらの措置の効果についてしっかり把握しながら必要な対応を行ってまいりたいと思います。
○倉林明子君 今の答弁ですと、令和八年度のところの処遇改善について言えば、期中改定もあり得るという御答弁だったかと思います。
二四年改定ということでいいますと、全体で一・五九%のプラス改定だったけれど、物価高、全国全産業平均の賃上げにも程遠いということで、再々議論にもなってまいりました。中でも在宅介護を支える訪問介護、この基本報酬の引下げということが現場のヘルパーに、国によって私たちは見捨てられたと、こういう受け止められたんですよ。尊厳が否定されたという思いなんですよ。離職を加速させているという実態に広がっていますよ。
そこで、私、期中改定については今後の検討ということになるのかと思うんだけれども、直ちに、検討を待たずにしてでもやるべきは、この訪問介護の基本報酬部分の引下げ、これ直ちに元に戻すべきだと、決断すべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 私、昨年もこの委員会のメンバーでありましたから、これまでも再三この委員会においてその議論がなされてきたということについては承知をしております。
その上で申しますと、この訪問介護の経営状況、地域の特性であったり事業規模、事業形態に応じて様々でございますので、状況に応じたきめ細やかな支援が必要だというふうに考えています。
このため、この報酬改定以降も、処遇改善加算の取得要件の弾力化、また物価高騰や賃上げに対応する支援、また先般の補正予算等による訪問介護事業所向けの各種支援などの対策に取り組んできたところでございます。
また、厚生労働省がこの訪問介護等に対してその改定検証調査の結果を行った、そのことを踏まえまして、中山間地域等の小規模な事業所の経営安定化を早期に図るための措置を講じましたほか、これらの取組の効果が現れるまでの間の資金繰り支援も念頭に福祉医療機構の融資を大幅に拡充してまいってきております。
引き続き、丁寧に把握、分析をしていきながら適切な対応を行ってまいりたいと考えています。
○倉林明子君 検証、分析の段階じゃないと思っているんですよ。はっきりしているのは、この訪問介護事業所のところの基本報酬が本当にこたえていると。ここを元に戻すということは即断すべきだということで求めているんですよ。
人手不足から、高齢者が在宅で介護サービスを受けたくても受けられないと、こういう事態、最悪の事態ですよ。断られると、頼んでもですね、要請しても断られると。断らざるを得ないと、事業所にしたらね。こんなことが起こっているんですよ。こういうのを保険詐欺と言われたって仕方ないと思いますよ。
そこで、さっきの緊急集会の決議の二に戻りたいんですけれども、期中改定までの間、賃上げの補助、これどうかということです。再々これも議論ありまして、今日も、令和六年度の補正予算の効果を見極めたいと、いろいろやっているからその効果を見たいという話ですよね。
そこで確認したいんですけれども、介護人材確保・職場環境改善等に向けた総合対策ということで補正予算が計上されました、一千百三億円。そのうち、人件費に充てることが可能だということで盛り込まれた八百六億円があります。これ執行状況について確認したい。交付の決定件数、補助金交付実績、直近でどこまで届いているかというのを確認したい。その上で、実際の現場際での賃上げ効果というのはどうですか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。
委員御指摘の更なる賃上げ支援、賃上げに向けて講じております令和六年度補正予算における支援につきましては、実施主体が都道府県となっておりまして、昨年末に成立した国の補正予算に基づいて、令和七年二月ないし三月の議会に都道府県が提出をした補正予算の受入れを経て、多くの自治体では四月に申請受付を行っているものと承知をしております。
現時点における国から四十七都道府県への交付額は七百七十一億円となってございます、全都道府県にということです。本年四月の介護関係団体の調査では、約九五%が補正予算による支援を活用予定としているなど、多くの事業所に活用いただけるものと承知をしております。
今後、本年の六月頃から順次交付され、本年夏頃には事業所に行き届くと見込んでおりまして、まずはこれらの措置が現場に行き届くよう取り組んでまいりますとともに、処遇等に与えた状況についての把握も予定してございます。
○倉林明子君 七百七十一億円、全県からの申請があった状況だと、行き渡るのは、今後、夏以降になるだろうと。
じゃ、その額ってどのぐらいで届きますかということですよね。これ一人当たり、常勤換算ということで、五・四万円ですよね。で、非正規にも回せる、ほかの職種にも回せるということでいうと、一人当たりでいうと五万円という規模、ずっと下がっていくんですよね。賃上げ効果、答弁なかったけれども、実質的な賃上げというとスズメの涙にもならないんじゃないかと、こういう声上がっているんですよ。
対象は、これ申請できる対象は、申請できるところはどこかというと、既に職員処遇改善加算も取っているというところになるわけで、介護事業所、これ四分の一については申請すらできないと、らち外に置かれるということですね。改めて、補正予算による賃上げ効果、これ見込めないから緊急集会開いているんですよ、見捨てないでくださいって言うわけですよ。こういうこと、こういう声に正面からやっぱり応えないといけない、いけないと思うんです。
現場のあらゆる職員の賃上げ補助として、一千百三億円確保しているわけですよね、補正で。現状、七百七十一億円についての報告はあったけれども、職場環境改善の取組の計画書の提出とか処遇改善加算取得とか、こういう要件というのは撤廃して、使える補正は全部人件費の向上に、つなぎとしてでも、賃上げ回せるようにするべきじゃないかと私思うんですよ。どうでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 補正予算による支援は、本年の六月頃から順次交付されるということでございます。現場の厳しい声を承っておりますので、速やかに行き渡るようにしていきたいと思います。
あわせて、この受給要件につきましては、より多くの事業所に申請していただけるように、事業所の事務負担に配慮して補助金の申請書につきまして各種様式を簡素なものとしましたほか、処遇改善加算の申請様式と一体化し、申請時点では処遇改善加算を取得していない事業所にあっても、令和七年度の加算取得と併せて申請をすることで補助金を受給できるような取組を進めさせていただいているところでございます。
○倉林明子君 いろいろやってもらったと、改善したと言うんだけれども、まだ、まだまだ事務手続も残っているし、対象外になっているところもあると。そして、五月八日の時点で、助けてくれ、見捨てるなということになっているというところで、遅いって言うんですよ。遅い、行き届いていない、足りない、そういう現状の認識を緊迫感を持って受け止めるべきだと思います。
私、そもそも加算で対応してきたでしょう、この人件費について、処遇改善については。介護職員のこういう加算でやっていくという処遇改善のやり方というのは、もう十五年以上繰り返されてきたという状況です。この加算というやり方で安定した人材確保につながってこなかったと、ここしっかり見るべきだと思います。
加算ではなくて、賃上げ財源というのは公費でしっかり確保していくべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 処遇改善加算につきましては、平成二十四年度改定で、平成二十三年度までの時限措置として、交付金により措置されていたものを介護報酬に組み込み、創設をされたものでございますが、これは、介護職員の処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるものではなく、事業者にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬において対応することが望ましいとされたことを踏まえ、措置されたものでございます。
この処遇改善加算はその全額を賃金改善に充てる仕組みとしておりまして、累次の取組によりまして介護職員の賃金は増加をしてきておりまして、令和六年度改定で講じた措置につきましても、令和六年度処遇状況等調査において、介護職員の平均給与は前年比で四・三%増と、各種取組の効果は反映されているものというふうに考えています。
一方で、賃上げに向けた取組は他産業が先行しているということは事実でございますので、処遇改善加算の要件の弾力化であったり、また先般の補正予算で賃上げに向けた支援講じているところでございまして、こういったことが早く行き渡るように、そしてその状況の効果も見極めながら、必要な措置講じていきたいと思います。
○倉林明子君 分かっていてその説明されているのかと思うとがっかりするんですけれども。
令和六年度の改定、二四年改定でやったときに、令和七年度の分も賃上げ想定してやったはずですよ。ところが、令和六年度は何とかさっきおっしゃったように賃上げ見合いできたかもしれない。七年度の分すっからかんですよ。ないですよ。だから、こういう声上がっているし、この加算というやり方じゃなくてきちんと人件費分を乗せるということをしないと、全産業平均は今八万円ですから、この格差をどうやって埋めるのかということを直ちにやらないといけない課題だという受け止めが必要だと重ねて申し上げたい。
介護給付の増加に連動して上がり続けてきたのが保険料なんですね。これ、第一号介護保険料は過去最高と今なっております。全国平均で基準月額は六千円を超えて、五千円以上というところが九割を超えている事態になっています。私、高齢者の負担はもはや限界超えているんじゃないかというふうに思うんだけれども、大臣の認識どうですか。
○国務大臣(福岡資麿君) サービスの質を確保しながら制度の持続可能性を維持することは重要だというふうに考えておりまして、その中で、御指摘のようなその負担という部分もその要素の一つとしてあろうかというふうに思います。
このため、令和六年度からの第九期介護保険事業計画期間においては、六十五歳以上の方々の第一号保険料について、所得再配分機能の強化や低所得者の保険料の上昇抑制の観点から、標準段階の多段階化、低所得者の標準乗率の引下げ等を行ったところでございます。こうした取組に加えまして、介護予防の推進であったり、健康寿命の延伸等を背景に、第九期計画期間と第八期計画期間を比較した第一号保険料の伸び率は、過去の計画期間と比較し、小さくなっているというようなデータもございます。
今後も、全世代型社会保障の理念に基づく負担能力に応じた給付と負担の在り方などについて、不断の検討を行ってまいりたいと思います。
○倉林明子君 最高額になっている大阪市は月額九千円です。段階増やしてもらっても、やっぱり平均上がっていますよね。軽減措置とったところでも、ただ、ゼロにはならないんですよね。月額やっぱり二千五百円程度になります、最低でもです。異次元の物価高が同時並行で起こっているという状況ですよね。加えて、必ず三年ごとに給付が増えていくという前提になって、これからまた高齢者も増えるので、給付も増えると、また保険料上がり続けるということになるんですね。これ、全体として今高齢者の暮らしを圧迫するということについて是非捉えるべきだということから指摘させていただきました。
改めて、この給付が増えるというところに対して、二〇一〇年、二〇一二年、民主党政権時代に自民党さんも公明党さんも提案されているんですね、公費負担を今の五割から六割にして保険料を抑制する。今こそこの観点が求められていると思うわけです。緊急に、国庫負担割合は一〇%にという引上げを今、今やるべきじゃないかということが一つ。
同時に、保険料や利用料の負担増、これが高齢者の介護サービスの抑制にもつながっているし、暮らしの圧迫にもつながっている。そういう意味でいうと、公費助成による賃上げや事業所の再建、介護事業所が消滅の危機にあるような自治体における事業継続に、これ保険の枠内じゃなくて、やっぱり公的な支援ということで早急に踏み込むべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員も再三御指摘いただいておりますように、その物価高騰などを踏まえると、介護事業者が大変厳しい状況に置かれているということは認識をしてございまして、これまでも補正予算による様々な支援などを行ってきたところです。
御指摘の、その介護保険における国庫負担割合につきましては、介護保険制度、この制度自体が社会保険方式の下、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところでございまして、そういった経緯を考えますと、この公費負担割合を引き上げることにつきましては慎重であるべきだというふうに考えております。
○倉林明子君 いや、かつて公約したことを思い出してほしいなと、今の方が緊急に求められていると、この点、重ねて言いたいと思います。
そして、今後、二〇二八年までに社会保障改革工程表ということでメニューが明示されております。利用者負担が二割から三割拡大していくということや、多床室、これニーズがすごく高まっている、負担があるのでね。それを、室料を、負担引き上げよう、金融所得や金融資産等に応じた負担増、こういうメニューが盛り込まれております。
私、介護が必要になった国民、ここに負担を増加させることによって、国民そのものがサービスを剥がされる、利用できない、国民そのものも見捨てることになっていくんじゃないかというふうに思うんですよ。こんな改革工程表の提案は断固撤回すべきだと、頑張れと、厚労省も、言いたいと思います。
それで、残った時間でマイナ保険証について質疑したいと思います。
マイナ保険証の電子証明書の有効期限が切れることで生じる二五年問題については、指摘をしたとおり、もう既に現場際では始まっておりまして、区役所等での更新手続に訪れる方々による混雑が起こっております。
医療現場では、更新忘れによってマイナ保険証で資格確認ができないトラブルというのも発生、増え始めております。保団連の調査によりますと、有効期限切れという回答があったと、資格確認ができなかった例の中でね、これ、医療機関の三割から既に報告があるというんですよ。
保険料を支払っているにもかかわらず資格が確認できない、こんなことはあってはならないと思うんだけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) マイナ保険証を利用する方々に確実に電子証明書を更新していただけるよう、電子証明書の更新を促す取組としまして、有効期限が切れる前に、有効期限前からの更新の御案内であったり、また、医療機関等を受診した際のカードリーダー画面での更新アラートの表示、こういった対応を行っておるところでございます。
また、電子証明書の更新手続を忘れ、有効期限が切れた後も、有効期限を過ぎてから三か月間は引き続きカードリーダーで更新のアラートを表示しながらお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に申請によらず資格確認書を発行する、こういったことをさせていただいています。
このように、従来どおりの保険診療が確実に受けられるように必要な対応を重層的に講じておりまして、マイナ保険証を安心して御利用いただけるように、引き続き、国民であったり、医療機関、双方に対して運用の周知や電子証明書の早期更新の呼びかけを行ってまいりたいと思います。
○倉林明子君 重層的な手続が結局医療現場の窓口で本当、非常にトラブルと同時に負担になっているという声、率直に上がっていますよね。従来の紙の保険証、これがあれば起こり得なかったトラブルなんですよ。
厚労省は五月十三日付けで事務連絡を出しております。自治体に対して、要配慮者等の資格確認書の、資格確認書の早期申請を促すというものです。
これ、後期高齢者に対しては職権交付という判断されました、延期されました。期限を延期ということでやっておられますけれども、申請を促すという前に、この後期高齢者に取った対応と同じように要配慮者に対しては職権交付とすべきではないかと思いますけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 資格確認書はマイナ保険証による受診が困難な方に交付をするものでございまして、マイナ保険証をお持ちでない方に加えまして、後期高齢者につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が高いことから、暫定措置として職権で資格確認書を交付することとさせていただいています。
それ以外の御高齢者の方であったり、障害者の方々などのこの要配慮者につきましては、資格確認書の必要性がそれぞれの事情に応じて異なりますことから、申請に基づき資格確認書を交付することとしております。
他方で、資格確認書の申請につきましては、親族等の法定代理人による代理申請のほか、施設職員などの介助者等による代理申請も可能としてございまして、また、申請によりまして交付された資格確認書の更新時には再度の申請は不要としてございます。ですから、一回目はお手間をお掛けしますが、その後の更新についてはもう申請を不要としているものでございます。
加えて、市町村窓口に申請が集中しないように前もっての申請の周知を市町村に促しておりまして、こうした対応も含めて、全ての方が安心して保険診療を受けられるようにしてまいりたいと思います。
○倉林明子君 いや、要配慮者のところにその後期高齢者と違うという説明は、私、よう分からぬかったですよ。
そういう意味でいうと、配慮が必要なところに申請しなさいって促すことで、代理もオーケーだとかいろいろ便宜図っているような言い方だけれども、逆ですよ。要は、後期高齢者にやった判断を要配慮者のところにまで広げるということの対応の方がどんだけ窓口も含めて要配慮者本人もトラブルなく医療機関にアクセスできるということになるわけですから、一歩踏み込んだ対応、私は強く求めたいと思います。
資格確認書の職権交付に踏み出す自治体が現れました。渋谷区等出ていますけれども、こういう動きに対して、こういう自治体に対して通知まで出して今マイナ保険証所有者に対しては申請に基づいて資格確認だということにしているんですね。私、合理的な事務扱い、トラブルを未然に防止するという観点からも、自治体が職権でこの資格確認書発行するというのは自治体の極めて判断としてあり得ると思うんですよ。自治権の範疇じゃないかと思うんですね。
その首長が地方自治体と、国保の部分での資格確認書を職権で加入者全員に交付すると、この判断を国として禁じることはできないと思うんだけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) この資格確認書は、制度の上では被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。
その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者につきましては、先ほども申しましたように、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、保有の有無にかかわらず、資格確認書を職権交付とするという暫定運用を行うこととしております。
国民健康保険の被保険者には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、同様の状況にはないというふうに考えておりますが、その個別の自治体の状況、これをしっかり把握しながら必要な対応を行ってまいりたいと思います。
○倉林明子君 いや、問いに答えていないですよ。禁じるんですかということを確認したので、それ押さえておきたいと思います。
今年度だけにとどまらず、二六年、二七年、膨大な更新切れ起こる可能性あるんですよ。これは政府の施行によってこういう混乱が自治体窓口に、そして利用者にかぶさってきているんですよ。職権交付ということを本当に拡大してこの時期乗り切るということでも必要だと思いますよ。どうですか。禁じるかどうか、確認。
○委員長(柘植芳文君) 申合せの時間が来ておりますので、よろしくお願いします。
○国務大臣(福岡資麿君) 先ほども申しましたように、制度上は被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付するとされていますから、この制度に沿った運用をしていただくというのが原則だということでございます。
その上で、今おっしゃったような自治体がどういう理由であるかということについて見極めた上で判断をしてまいりたいと思います。
○倉林明子君 自治体の判断を尊重すべきだと。
終わります。