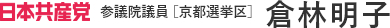自治体の人材不足ー三位一体改革で進められた人員削減(2025/2/26 行政監視委員会)
日本共産党の倉林明子議員は、26日の参議院行政監視委員会で、国と地方の行政の役割分担について、参考人質疑を行いました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子でございます。
今日は、京都から窪田先生、ありがとうございます。そして、お二方の参考人の皆さんも、示唆に富んだ御意見ありがとうございます。
最初に、京都からということで窪田参考人にお伺いしたいと思います。
私、先ほどのプレゼンというか、これ意見表明の最後におっしゃられた、今地方がもたないときが来ていると、この危機感は本当に共有するものなんですね。改めて、今こういう状況になったところの、人口がピークだったというときに始まった三位一体改革ですよね、交付税の大幅な削減、そして人員削減とセットでこの行政評価が持ち込まれてきて、先生がやっておられたというその行政評価、京都市における市政評価、私、市会議員でしたので始まったときから関わってきた経過もありまして、この結果がどういうふうに活用されたかというと、施策の見直し、つまり縮小、統合という方向に予算の削減という手法で使われてきたというのが体感的にあるんですね。
そこで、当時の市長は、一生懸命この行革取り組まないと地方行政もたないという意識の下で、自分でも口にされていましたけど、自治体職員の削減について、乾いたタオルが絞るような削減が要るんだと、まさにそういう切り込み方をされてきて、現状どうかというと、やっぱり人材不足は、京都市に限らずですけれども、自治体職員の人材不足、とりわけ技能職のところというのは、水道や下水のところで事業の存続、継続ができるのかというふうなところさえ生まれてきているということあると思うんですね。
今の地方がもたないというような状況の要因に、私、三位一体改革と一緒に進められてきたこうした様々な取組が一つ要因としてあるんじゃないかという問題意識を強く持っているんですけれども、先生、御意見をお聞かせいただきたいと思います。
○参考人(窪田好男君) お答えします。御質問ありがとうございます。
実際、難しいところであろうと思います。ただ、私自身は、その三位一体改革も含めて、この人口の急減そして地方創生全般についても、例えば子供を産む産まないにしても、住む場所にしても、それぞれの希望をかなえる、強制はしないという形でずっと進めてきているわけですので、政策等の影響を受けつつも、私たち国民一人一人の選択の結果なんだろうと。そして、そこに対応している政策として三位一体改革や様々な取組がなされてきたのではないかと思っています。
そして、その中で、いや、正直無理じゃないかなとか思いながら様々な自治体に行っておりますと、例えば、全ての事務事業に一番から百番まで順番を付けてくれたら行革ができるとか、いや、無理ですって若いときには真っ正面から言って、今ならできると言うかもしれませんけど、はいってお答えを申し上げたり、三百三十億円ぐらいの財政規模のとある市において、財政再建のためには事務事業評価で三十億円をカットして、そしてサービスのレベル低下は一切しないようにしてくださいと言われたら断るんですけど、できますと横に並びながら宣言されてしまうと頑張りますと答えたりするんですが、そうなかなかその政策評価にも無理があるなというように思いながら取り組んでまいりました。
そんな中でも必要性や重要性があるという部分は、最後に、資料には書いてございませんでしたが、先ほどの意見陳述の最後のところに、自治体評価とそのEBPMはこういう意味があるのではないかと申し上げて、それははっきり思っているところです。
そして、無駄と先ほど石井委員の御質問の中で言われると、きついなと言いながら私ども参考人は答えましたけれども、様々な観点から、人それぞれの考え方から無駄とかがあるのも事実でございます。そうした中で、ここまでは乾いた雑巾を絞ったり少人数でマネジメントをしたり、一人二役、三役をこなしたりみたいなことをやってきたけれども、随分限界が来ているのではないかと思っています。そんな中でAIとかドローンといったようなデジタルでどこまでできるかということを試して、それでもやっぱり難しい中で次何があるんだろうということに思いをはせている、また考えを向けているところでございます。
そこで、御質問と少しずれてしまうかもしれないことをお許しいただくのならば、誰かがやはりこの言いにくいことも言い、憎まれなくてもいいのかもしれませんが、憎まれ役も担いということをせねばならず、そういうときに地方からのその発言を待っていても難しかろうというようなことを思ったりする中で、国の大胆なビジョンや公共政策をと申し上げたのは、そうした点を意識していたからでございます。
済みません、お答えになっていないかもしれませんが、お許しくださいませ。
○倉林明子君 ありがとうございます。
やっぱり大きな財源、分権改革に伴って、地方に権限を移譲するということと併せた財源移譲が余りにも不足してきたということがやっぱり大きかったなというふうに改めて思っているということは表明しておきたいと思います。
今日は、飯島参考人から大変地方創生に関して示唆をいただいたなと思ってお聞きしました。
計画と交付金による集権化というような課題の指摘や裁判的統制の難しさがあるんだという課題の指摘と併せて、地方創生二・〇については、この国会の行政監視機能、行政監視への期待ということで、国会の統制の可能性があるということで、御指摘いただいたことを更に深めて、地方分権と行政、先ほどの行政改革の話もそうなんですけれども、権限と分権と財源、それから国会の統制機能ということを更に深めて勉強させてもらいたいなと思いました。
そこで、今日はお聞きしたいのは、飯島参考人にお聞きします。
法律時報に寄稿されていた「コロナ対応から考える地方自治の課題」というものを興味深く読ませていただきました。この法律事項に属する事柄を行政立法によって定めたり、権限の連結、濫用に相当するような法律の執行がなされるなど、法治主義に反する行政事象が観察されたと、文章の中でこういう指摘がされているんですね。これ、それぞれ具体的な事例ということでいうと、どういうものになるのか、御紹介いただければと思います。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。
今のこの法治主義に反するような事象ということですけれども、具体例として見てきましたのは、コロナ禍で、特に新宿の繁華街などで人流抑制をしなければならないといったようなときに、風営法違反ということで店に立入検査をしたというようなこと、そこはかなり問題になった事例ではないかと思います。
本来、法律、法規でもって人の権利義務に関する定めをしなければならないところを、なかなかその法律がない状態の中で、行政立法であればまだよろしいかと思いますが、通達、事務連絡のレベルで、要請という形も取りながらではありますけれども、実質的なその権利制約、自由の制約ということが行われたということは広く観察されたところだと思っておりまして、そういった点の問題を指摘したところでございました。
ありがとうございます。
○倉林明子君 ありがとうございます。
コロナ禍の中で浮き彫りになったのが、平時の際の保健医療や福祉の提供体制、この脆弱さだったなと思っているんですね。
そうした中で、私は、現場をより混乱させたというのが乱発された事務連絡なんです。厚生労働省からは膨大な事務連絡が、毎日どころか、いろんな部署からどんどん来るわけですね。さらには、先ほど御紹介もあったように、内閣府からの事務連絡もあると。この事務連絡を見ないことには仕事ができないとか、予算もそれに伴って付いてくるというようなこともあって、極めてこの事務連絡が現場を混乱させたなという思いを持っております。
こうしたやり方ということについて、法制度の建前ということで飯島先生は御紹介もされているんだけれども、建前から見てどんな問題があったとお考えか、教えていただきたいと思います。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。
確かに、国レベルにおいても極めて資源が制約されている中で、情報ですとかその知識というものがない中で法規という形で出すのでは、そこには行き着かない。ですので、まずその目の前の課題に対応するために事務連絡という言わばインフォーマルな手段を用いざるを得ないという状況はあっただろうというふうに思います。
ただ、その事務連絡はあくまで事務連絡であって、法的拘束力はないものではありますが、今、倉林議員御指摘くださったように、地方公共団体、受ける側としてはそれに実質的には従わざるを得ないという状況がありましたので、その関与という言葉を取れば、その関与という意味において、法的拘束力のないものでもって、実質的には要請という形を取りつつ強制するというところでの非常に大きな問題ははらんでいたものだろうというふうに認識しております。
以上でございます。
○倉林明子君 私、一番この論文の中で興味引かれたのがフランスとの比較のところなんですね。
日本とコロナ対応が対照的だということでフランスの対応が紹介されておりまして、フランスにおいて、「緊急事態 制約下での民主主義」ということが出てくるんですけれども、これは、こういうフランスにおけるその緊急事態の制約下における民主主義というのがどう担保されたのか、日本との違い、決定的、対照的だとおっしゃるその違いは一体何なのか。余り時間もありませんけれども、この表現だけではちょっと分かりにくかったので、教えていただければと思います。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。
日本法の特徴として、インフォーマルであると、自粛要請という形で実質的に人を動かす規範の定立もし、規範の執行もするという特徴があるのに対して、フランスは、国会でその法律を制定し、それは訴訟がかなり多く提起されまして、裁判所がその担保をするという意味での法治主義というものがその危機下においてもそれは維持されたという、その意味でも非常に対照的であるというふうに考えて論文を執筆したところでございます。
ありがとうございます。
○倉林明子君 ありがとうございます。
ちょっと具体的なところでいうと、裁判所が機能したかどうかというか、法の、法治というところが機能しているかどうかということでいいんでしょうか。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。
フランスは行政裁判所制度ですけれども、その行政裁判所が通常の平時においても非常に日本とは比べ物にならない機能を果たしておりますが、その危機下においても、市民の側からの訴訟の提起というものがもちろんあったわけですけれども、それに対して行政裁判所がきちんと、憲法裁判所も含めてですけれども、法治主義を守るという意味での機能を果たしていたと一定の評価はできるのではないかと思っております。
○倉林明子君 コロナの対応を踏まえて、司令塔の強化ということでの法整備が日本では進められたということになりました。これ、国の権限強化という方向でもあって、地方自治の権限ということでいうと逆行するものではないか、権限強化ということから逆行する方向になるんじゃないかという指摘も、本当そのとおりだなと思うんですね。
一時的な権限強化、有事のときの権限強化という中身での提案ではあるんだけれども、この国家行政権の強化を図るという方向での法改正について、飯島参考人の御意見、最後伺って、終わりたいと思います。
○参考人(飯島淳子君) ありがとうございます。
この国家行政権の強化、具体的には内閣感染症危機管理統括庁など、厚労省の組織改編というところであると思いますが、やはりその危機の特に初動時に今回も非常に混乱した、特に国と地方公共団体、知事との関係ということが連日のように問題として報道されたということもございましたが、やはりその危機の特に初動時において、今回の改正では、国の側で企画立案から執行までできるような体制を整えようということではあっただろうというふうに思います。
もちろん、この危機時に限っての集権化ということで必要性はあるとはいえ、もちろん初動時においても、まず現場を見ているのは自治体でありますので、そちらの情報と極めて密接なコミュニケーションを取りながら権限を行使されるようにしなければならないと考えております。
以上でございます。
○倉林明子君 西出参考人には質問する時間が取れませんでした。申し訳ありません。
ありがとうございました。