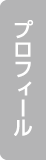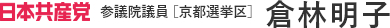補聴器に国としての公費助成を(2025年4月3日 厚生労働委員会)
日本共産党の倉林明子議員は3日の参院厚生労働委員会で、加齢性難聴者への補聴器購入の助成について、自治体任せではなく、国として公費補助をするよう求めました。
倉林氏は、高齢者の質の高い生活と認知症予防に、早期の補聴器利用が有効だとの指摘がある一方、補聴器は片耳でも3万~20万円と高額だと強調。「世界各国と比べても補聴器の普及率が低い要因に、公費助成の違いがあるのではないか」とただしました。
倉林氏は、日本補聴器販売店協会の調査で、18歳以上を対象とした補聴器助成の実施自治体は、2024年12月1日現在で390に拡大し、新潟県では全ての自治体が実施しているとして「国の調査は21年度以降実施しておらず、民間だけが調査していることは問題だ」と批判しました。地方議会で補聴器購入に対する国の制度拡充を求める意見書が、20年以降233件になることを示し、国はこれに応えるよう求めました。
福岡資麿厚生労働相は、自身も補聴器をつけているとして「聞こえが良くなることで環境が変わることは認識している。難聴者が充実した生活を送れることは重要だ」としながらも「公費での助成が適切かどうか各自治体の取り組みを注視する」との答弁にとどまりました。
また、倉林氏は、マイナ保険証による資格確認トラブルが続いていることを指摘。「システムの欠陥を認め、資格確認が確実に行われるよう従前の保険証を復活させるべきだ」と強調しました。
今日は、加齢性難聴について質問したいと思うんです。
これ、資料を付けておりますけれども、これは日本医師会の意見広告です。日本における加齢が原因の難聴者は千五百万人以上とあります。そして、米印のところで、六十五から七十四歳では三人に一人、七十五歳以上では半数以上に上るというものです。日本医師会は、ここにありますとおり、聞こえにくい、それは認知症予防の第一歩と警鐘を鳴らしております。高齢者の生活の質を高めて認知機能の悪化の防止につなげる、そのためにも、加齢性難聴者を早期に発見する、そして早い段階からの補聴器利用につなげていくということが極めて有効だとされております。
そこで、質問です。加齢性難聴者に対する補聴器の普及率というのはつかんでおられるでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答え申し上げます。
身体障害者福祉法に基づく両耳の聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など聴覚障害に重度の障害がある方は、令和四年度において約三十一万人と推計されております。その中で補装具として補聴器を支給している件数は、令和五年度において約五万件と承知をしております。
なお、身体障害者福祉法に基づく聴覚障害の基準では加齢性難聴か否かを考慮しておりませんので、加齢性難聴の方に特化した数字は把握してございません。
○倉林明子 そうなんですよね。認知症予防の大きな効果も指摘されているんだけれども、加齢性難聴ということでいうと一体どのぐらいなのかと、で、そこに対しては補聴器が普及、どの程度になっているのかというの、政府は持ってないんですよね、数字ね。
そこで、調べてみますと調査しているところがありまして、これは日本補聴器工業会というところで、継続的に調査取っているんですね。推計にはもちろんなるんだけれども、この二枚目の資料のところに入れているように、世界との比較を取っているんです。で、日本で見ますと、難聴者の比率ということでいうと、そんなに特段高くない、平均的なんですね。ところが、補聴器の普及はどうかということで見ますと、下から二番目ということで、大変低いというのがこの調査では明らかになっているんですね。
それで、一体どんな差があるのかということでもう一つ、これは別の調査で調べてホームページ上で公開されているものですけれども、各国の補聴器購入費用助成制度、対象範囲ということで、三枚目の資料付けております。これ、対象範囲ということでいうと、軽度難聴から対象にしているというものが多いんですね。で、額も比較的大きく負担をしているというところが、実はこの普及率が高いというところともリンクしているものとして見れると思うんです。
そこで、補聴器の値段というのがとても高いんですね。片耳当たり三万から二十万、平均的なものですよ。高いのは七十万とかするものもあります。両耳でも四十万から五十万ということになりますので、これ極めて高いためにアクセスできないと。
で、今補聴器を利用されている方はどういうふうに感じておられるかといったら、補聴器がなかったら孫との会話も楽しめないし、社会参加も諦めざるを得なかったと、使った人からはこういう声が上がっているんですね。
難聴者の発生する比率というのは余り変わらないと見れるんだけれども、補聴器の普及率が極めて低いという状況の一つの要因に公費助成の違い、各国の、これ格差につながっているんじゃないかと言えると思うんですけれども、大臣、認識はいかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 委員が御指摘いただきましたこの資料につきましては、民間団体が実施した調査でございまして、分母となる難聴者の定義がどのように設定されているか等も明らかではないため、本調査結果に対する評価を述べることは差し控えたいと存じます。
その上で、我が国におきまして、高齢者を含め身体障害者手帳の交付対象となる聴覚障害がある方に対しましては、障害者総合支援法に基づく補装具支給制度によりまして補聴器を利用していただくことが可能でございまして、その購入や修理に要した費用に対しまして利用者は原則一割負担としているところでございます。
各国の施策についてはそれぞれの事情に応じて異なるものというふうに考えますが、いずれにしましても、補聴器を必要とされる方がこれらの支援制度につながるように、引き続き周知等に努めてまいりたいと思います。
○倉林明子 認知症予防に大変効果があるということは明らかになっていると思うんですよ。さらに、アプローチとして、重度のレベルに達する前にこれ補聴器を活用するということが更に有効だということで各国での取組も進んでいると思うんです。
まず、データないんだから、民間がやったデータは信用できないというんだったら調査掛けたらどうでしょうか。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答えいたします。
令和二年度に当方で実施いたしました調査研究事業の中では、千七百四十一の自治体を対象に、難聴の高齢者の補聴器購入に係る助成、あるいは難聴である高齢者の早期発見のための施策の実態等について調査をいたしております。
それによりますと、回答を得た九百四十の自治体のうち、調査当時の時点において補聴器購入の公的助成を行っている自治体は三十六でございました。
○倉林明子 その調査の実態、調査も見ていますけれども、それは自治体が助成制度をどうやっているかということを調べられたもので、要は、補聴器が必要な加齢性難聴の方々というのは一体どのぐらいおられるのかと、そして、認知症予防にもつながっていくような、要は施策を展開する上での必要なデータを持ってないわけだから、それ調べたらどうかということでしたので、改めて答弁があればしていただければと思います。
今お話あったように、国の制度、まして調査もされていない中で、地方自治体では独自の助成制度が広がっております。先ほど紹介あった二〇二一年の厚労省の調査によりますと、既に実施に踏み出しているという自治体は三十六ありました。これ、二〇二一年のデータです。
直近のところ、つかんでおられますか。併せて答弁ください。
○政府参考人(黒田秀郎君) お答えいたします。
先ほど申し上げた令和二年度の調査と同様の調査ということでいいますと、その後の行われている調査はございません。
あと、先生が御指摘いただいたその民間の団体の調査というものもあろうかというふうに承知をしておりまして、そういう中では取り組んでいる自治体が増加をしているという話は伺っておりますが、民間団体の調査でございますので、その評価については様々あろうかと存じます。
○倉林明子 そうなんですよ、民間しかやっていないんですよ。そこは大変問題だと、民間がやっているデータだから信用できないということにしておいていいのかと思います。
日本補聴器販売店協会というのが、民間ですけれども、継続的に調査をされております。十八歳以上を対象として助成制度を実施している自治体は、二〇二四年十二月、これ直近のところ調べていまして、何と二一年は三十六自治体だったのが、今三百九十自治体まで拡大しているんですね。新潟県内では全ての自治体で助成制度を持っているということにまで広がっています。
さらに、地方議会からの国の制度拡充、国の制度としてつくってほしいという意見書も相次いで寄せられておりまして、令和二年度以降、二百三十三件に上っております。府県議会レベルでいいますと、和歌山、岩手、兵庫、埼玉、奈良、三重、京都、七つ上がっています。そして、政令市では、名古屋、京都市会ということで寄せられているんですね。
加齢性難聴者の補聴器購入に対する国としての公的補助制度、私は、しっかり調査もできていないということ大変問題だと思うけれども、ここまで自治体の中で広がってきている、要望も出ている。こういう公的補助制度、国としてつくるべきだと、この声応えるべきだと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 私自身も元々耳が余り聞こえなくて、今も補聴器付けているんですけれども、元々やっぱり付けていないときに比べて、付けると大分やっぱり聞こえが良くなることによって環境が随分変わるということは十分認識をしてございます。そういう意味において、加齢性を含む難聴者の方々が日常生活であったり社会生活を自立して送っていただくようにするということは極めて重要だというふうに思います。
先ほど申しましたように、これまでも、総合者総合支援法に基づく補装具費支援制度による補聴器の購入費用の助成に加えまして、販売店の従業者さん向けに高齢者に適切に補聴器を利用していただくための手引の作成や研修を行うほか、自治体が難聴の高齢者の早期発見などに関する取組を開始する際に参考となる手引の作成などを行っておりまして、引き続きこういった取組を進めていきたいと思います。
一方で、御高齢になりますと、聴力であったり視力の低下など様々な身体機能が低下をいたしますが、こうした問題の対応一つ一つについてその公費による助成を行うことが適切かどうかということについては様々な御意見があるところでございます。今おっしゃいました各自治体の取組とかもしっかり注視してまいりたいと思います。
○倉林明子 共生社会の実現を推進するための認知症基本法、これみんなで苦労して作りまして、当事者も参加して作った画期的な法律だと思っているんですけど、これ昨年の一月から施行です。基本理念、そして、認知症の意向を十分に尊重しつつ、保健サービス、福祉サービス、これ、充実、切れ目なく提供されるようにしてくれと。これ本当、補聴器購入助成というのは、この認知症の共生社会実現目指すというこの基本法にも応える一歩になるということを強く強調しておきたいと思います。
そこで、残りの時間、マイナ保険証について聞きます。
マイナ保険証の利用をめぐるトラブル、これ、昨年十二月二日、健康保険証が発行停止以降も続いております。いつも調査していただいています全国保険医団体連合会、保団連の調査によりますと、九割の医療機関でトラブルが発生しているということです。深刻だなと思っているのは、資格が無効という表示が四割弱で出ていると。そして、新たに増えているのが、電子証明書の有効期限切れ、これが三〇%もあったというんです。保険証なんですよ。資格があるにもかかわらず、資格が確認できないと。窓口で十割負担を求められた事態、これが千七百二十件にも達していたということなんです。トラブルの解消、まだできていません。これ、大臣、どう認識しているかということを聞きたいのと、併せて聞きます。
これね、総務省によりますと、二〇二五年度はマイナンバーカード十年の期限による更新が一千二百万件です。これは二四年度の四倍を超える規模になるわけです。さらに、五年で更新が必要となる電子証明書の更新、これが千五百八十万件。極めて、更新時期、本体の更新、そして証明書の更新ということで、ダブりですごい数になるんですよ。極めて、マイナ保険証の漏れ、確認ができないというような事態が発生するリスクというのは今年極めて高いんです。そういうことでいいますと、資格確認できないという事態が更に拡大しない、させない。そのためにも、保険証ですね、今でも保険証で確認していますから、これまでの従前の保険証あるいは資格確認書で。これ、保険証復活して、マイナ保険証を選択した人にも漏れなく交付しておくと。これが現場でのトラブルを未然に防ぐ最大の手段になると思うんだけれども、いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 今マイナ保険証を基本とする仕組みに移行したところでございますが、マイナ保険証の利用促進と併せて、マイナ保険証をお持ちでない方には、当分の間、申請によらず資格確認書を発行することであったり、何らかの事情でマイナ保険証で資格情報の確認ができなかった場合には、保険証でなくても十割負担ではなく適切な負担割合で円滑に保険診療を受けられることとしておりまして、そうした取扱いを医療機関、国民双方に対してしっかり周知していきたいというふうに思います。マイナ保険証が使えず患者さんが不利益を被ることがないよう、引き続き、国民の皆様や医療機関等に対して丁寧な周知を実施してまいりたいと思います。
そして、マイナ保険証を利用される方に確実に今電子証明書を更新していただけますように、電子証明書の更新を促す取組といたしまして、有効期限前からの更新の御案内であったり、医療機関等を受診した際のカードリーダー画面での更新のアラート表示といった対応を行っております。さらに、電子証明書の更新手続を忘れた方につきましても、有効期限を過ぎてから三か月間はお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とするほか、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に、申請によらず資格確認書を発行することとしてございます。
このように、紙の保険証によらず、従来どおりの保険診療が確実に受けられるように、必要な対策を講じてまいりたいと思います。
○倉林明子 確実な資格確認ができるというのが保険証ですから、それ担保する紙の保険証ということをきちんと今のマイナンバーカードしか持たない人にも今配付しておくということが極めて資格確認に有効だ、重ねて、今年、今やることだと申し上げて、終わります。
※資料があります