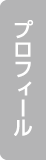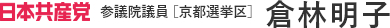医薬品承認制度の後退、規制緩和を批判 (2025/5/13 厚生労働委員会)
改定医薬品医療機器等法(薬機法)が14日の参院本会議で自民、立民など各党の賛成多数で可決、成立しました。日本共産党、れいわ新選組などは反対しました。日本共産党の倉林明子議員は13日の参院厚生労働委員会で、医薬品の承認制度の後退と医薬品販売の規制緩和を批判しました。
倉林氏は医薬品の承認の要件として「臨床試験の試験成績」を必要とする条文を削除する問題で、検証的臨床試験により安全性・有効性を確認することは薬事承認制度の根幹だと指摘。それを変更し、厳密なエビデンス(証拠)が確認されないまま新薬が承認され流通すれば、患者を危険にさらすと批判しました。福岡資麿厚労相は「どのようなデータを求めるかは個別の承認審査の中で判断する」と述べるにとどまりました。
医療用薬品から市販向けに転用されて間がない要指導医薬は、薬局での対面販売が義務づけられていますが、改定法ではオンラインで服薬指導を受ければネット購入が可能。一般の市販薬についても条件を満たせば薬剤師がいないコンビニでの販売も容認します。
倉林氏は、若者を中心としたオーバードーズ(過量服薬)の問題が焦点になるなかで、乱用の助長につながりかねないと指摘しました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
条件付承認制度の見直しについて質問したいと思います。
衆議院の答弁では、令和元年に導入した条件付承認制度の実績がないとして、米国等と同様の仕組みに見直すと説明されております。米国におけるこれ迅速承認された抗がん剤が一体どれだけあって、そのうち五年以内に有効性を示せなかったものというのはどれだけあるのか、実績つかんでいるのか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
これは論文を基にしたお答えにはなりますが、二〇二四年四月に米国の医学雑誌であるJAMAに掲載をされた論文によりますと、二〇一三年一月から二〇二三年七月までに米国で迅速承認された抗がん剤は百二十九品目でございました。そのうち迅速承認後五年以内に検証的な結果が得られなかったものが十七品目であるというふうに報告されていると承知をしております。
○倉林明子君 論文の紹介ありましたけれども、これ、私ね、そもそも、アメリカに合わせるということである場合ですよ、この迅速承認制度に対する検証が十分にされる必要あると思うんですね。
今紹介あったように、百二十九件中十七件という数字が論文であるんだということでしたけれども、少し前の文ですけれども、医学雑誌のブリティッシュ・メディカル・ジャーナルのところにも査読済みということで出ている調査結果がありまして、これ見ると、二〇二〇年までに承認された二百五十三件中取消しが十六件で、およそ半分の百十二件については有効性未確認と、こういう調査報告もあります。これ、中には、義務であるにもかかわらず臨床試験が未実施のものさえあったと、こういう衝撃の中身になっているんですね。
改正法案第十四条の二の二で、この条件付承認制度を見直し、適用、見直して適用条件緩和するということで、薬事承認のこれまで要件としてきた第三相試験を実施可能な場合であっても実施しなくても承認可能だとしているわけですが、これ、安全性、有効性大丈夫だという根拠は一体何なのか、御説明ください。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
今回の見直し後の条件付承認制度におきましては、有効性につきましては効能又は効果を有すると合理的に予測できるものであることといたしますが、安全性につきましては臨床試験及びその他の安全性試験データ等も踏まえて承認をすることとしておりまして、製造販売後に得られるデータから有効性を確認する仕組みにつきましても現行制度と変更はないものでございます。評価に必要な臨床試験自体を省略することは想定をしておりません。
また、条件付承認を行う際にどのようなデータを必要とするかにつきましては、これは従来より個別品目ごとに判断をすることといたしておりますが、臨床試験の結果を踏まえて従来の一定程度の有効性、安全性を確認するという基本的な考え方は改正後も変わらず維持されるものでございます。
○倉林明子君 いや、そうやって衆議院でも答弁されていて、これまでと変わるものではないと、この間の質疑でもそういう答弁ありました。
しかし、これ、要は、データとは言うんだけれども、第三相試験は実施可能であっても実施しなくても可能だということになっているわけですよね。その上、第二相試験、つまり、第二相試験だけでは有効性、安全性、これ十分と言えない、とりわけ安全性、そういうことで第三相試験を承認の要件というようにしてきたわけですよ、これまで。
にもかかわらず、衆議院の質疑で、我が党の田村委員が確認しましたところ、この二相試験さえもやらないこともあり得るんだという答弁があったわけですよ。私、更に重大だと思っておりますのは、医薬品の承認の要件ということで、原則的には第十四条の三項が規定になっていると思うんですけれども、ここで臨床試験の試験成績とこれまで明記されていたわけですよ。これが削除されているんですね、今回。薬事承認のこれ根幹部分の大幅な変更だというふうに受け止めざるを得ないと思うんです。
今後の医薬品の承認、これがリアルワールドデータのみと、こういう臨床成績によって承認が、申請が可能となるのかと、可能となるんじゃないかと、条文上は。いかがですか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
現行の薬機法の下でもリアルワールドデータを用いた承認は可能ではございます。
その上で、今回、令和七年一月の医薬品医療機器制度部会でのとりまとめを受けまして、ランダム化比較試験による厳密なエビデンスの重要性に留意した運用や、信頼性確保に向けた継続的な取組を前提としてリアルワールドデータの利活用が明確化されるよう、法律上の承認申請時の添付資料の規定において、臨床試験の試験成績に関する資料という文言を医薬品の品質、有効性及び安全性に関する資料という文言に変更をし、より一般的な規定に見直すこととしたものでございます。
今回の法改正後におきまして、承認のための有効性、安全性の確認のレベルは現行制度における各承認制度と変わりないものでありまして、科学的な根拠のないものを安易に承認するものではございません。
○倉林明子君 条文が変わるのでそういうこと可能になるんじゃないかと、これは薬害オンブズパースンからも厳しい指摘もあるところです。
なので、改めて確認しているんですけれども、削除するということで、検証的な臨床試験、この実施というのは有効性、安全性を確認する、このための承認制度の私は根幹を成すものだと思うんですよ。現状ではリアルワールドデータというのはランダム化比較試験の代わりにはならないと思うわけです。少なくとも、これ使うということ、代わりにするというようなことは、科学的な合意という点では得られていないものだと思うわけです。
検討会の中でも意見出されていましたけれども、ランダム化比較試験の実施が難しいからといってリアルワールドデータを用いた観察研究のエビデンスでよいとする考え方は、有効性、安全性に関する厳密なエビデンスの必要性を軽んじ、中長期的には新薬開発を妨げると、こういう意見の紹介もありました。
私ね、厳密なエビデンスが確認されないまま新薬が承認されれば、医薬品としてこれ流通することになるわけですよね。患者を危険にさらすことにつながりかねないというふうに思っているわけです。大臣、認識いかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 今回の条件付承認に係る見直し後においても、その承認時には、先ほど局長も申し上げましたように、データを踏まえて承認する際の有効性、安全性の確認のレベルはこれまでの条件付承認と変わりはございませんで、十分に有効性、安全性を確認するということが前提であります。科学的な根拠がないものを安易に承認することはございません。
こうした考えの下で、条件付承認時に検証的臨床試験を求めるかどうかを含めまして、どのようなデータの提出を求めるかについては、個別の承認審査の中で、薬事審議会の意見を聞きながら判断することとなります。
有効性及び安全性が確保された医薬品を迅速に届けられるように、適切に運用に取り組んでまいりたいと思います。
○倉林明子君 いや、条文そのものを変えるので、そういうことがもう可能になっていくと。姿勢として表明されるのはいいんだけども、法改正によってリアルワールドデータだけでも申請、承認可能になっていくんじゃないのということ、これ道としては開かれるんじゃないかということで、それ、要は、担保をする、その条文上の担保がなくなるということがリスクとして高いということを言っているわけですよ。
これ、新薬が承認されれば、アメリカでもそうなんですけども、医薬品として販売が可能になるということがスタートしますよね。数年後に、先ほど紹介したように、安全性、有効性という観点から否定をされて承認取消しと、こういうことも実際起こっております。その間の製薬大企業が得る利益というのは、抗がん剤などであれば膨大なものになっているわけですよね。何よりも私は優先されるべきは薬剤の安全性と有効性だということを重ねて申し上げたい。
大臣に改めて確認したいと思いますのは、一九九九年、厚生労働省に設置された薬害の誓いの碑、ここには、命の尊さを心に刻み、サリドマイド、スモン、HIV感染のような医薬品による悲惨な被害を再び発生させることのないよう、医薬品の安全性、有効性の確保に最善の努力を重ねていくことをここに銘記する、こう記載されております。
何でこうした碑を建立することになったのか、いかがですか。
○国務大臣(福岡資麿君) 御指摘ありましたこの誓いの碑は厚生労働省の前庭に設置をされておりますが、薬害エイズ事件の反省から、医薬品による悲惨な被害を再び発生させることのないよう、医薬品の安全性、有効性の確保に最善の努力を重ねていく、この決意を示すために平成十一年八月二十四日に建立をしたものでございます。
○倉林明子君 薬害エイズ事件のような事件の発生を反省し、この碑を建立したとあります。そのとおりだと思うんですよ。この碑の建立からもう四半世紀となろうとしております。改めて、薬害根絶の私は決意が問われているんだということを申し上げたいと思います。
有効性、安全性の後退は許されないと思いますが、一方、患者が自ら安全性と有効性の情報を十分に理解した上で治験に参加する、このハードルは現状余りにもやっぱり高いと思うんですね。実際に、治験情報の提供不足だけじゃなくて、治験実施している病院が非常に遠いなどと、治験を諦めるという人も少なくありません。受けたいという要望も強いです。
治験に参加したい患者が参加しやすい、こういう環境整備に向けたインセンティブの検討も必要ではないか、許可すべきじゃないかと思います。いかがでしょう。
○国務大臣(福岡資麿君) 医薬品の有効性、安全性の確保のため、条件付承認制度により承認されました医薬品について、条件として付された臨床試験等が速やかに実施されることは大変重要なことだと考えています。
このため、例えば、承認時の条件として求める試験等に対して期限を設けるということであったり、また、試験等の実施状況の定期的な報告を求めるということ。また、条件が付された試験を市販後の医薬品リスク管理計画において管理するなどをすることによって条件として付された試験の進捗状況を管理し、試験の速やかな実施を促してまいりたいと思います。
○倉林明子君 そういうことじゃなくて、今、実際に治験を受けたいと、そういう薬がどこにあるのかと、どこに行ったら、まだ治験段階だけれども受けられるという、そういう要求強いわけですよ。衆議院で参考人質疑でも、そういう段階のもの、副作用は分かっていたけれども使ったという紹介もありましたけれど、そういう情報と併せて、治験の件数がなかなか確保できないというようなことも、これ条件付承認制度を導入するというときも議論ありました、条件にするということで。
そうじゃなくて、治験がしやすい環境、治験が受けやすい環境、こういうところをもっときちっと条件拡大するべきではないですかということを申し上げているので、ちょっと今、答弁違うんですけど。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
治験につきましては、その実施状況等を明らかにして治験の透明性を確保していくことというのは、国民や医薬関係者の治験へのアクセス向上、治験の活性化に資するということから、薬機法の施行規則第二百七十二条の二に基づきまして治験の届出をした者は治験に関する事項等を公表することとされております。
この情報の公表、重要でございます。引き続き、これは患者団体や研究者の意見を伺いながら、システムの機能向上等に向けた必要な監視を行って治験情報を国民に適切に届けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
○倉林明子君 それだと余り変わらないと思うんですね、これまでの環境からして。やっぱり、どうやって治験を拡大していくか、条件整備していくかということがあって、あってですよ、それでもやっぱり無理だということで踏み込むラインを越えちゃっているんじゃないかと思うので、あえてこの質問をさせていただきました。
その上で、本法案では、市販後安全対策、これを講じつつ製造販売するとしているわけですけれども、現状はどうかと思うんですね。大きなパンデミックもありまして、新型コロナウイルスワクチンがたくさん使われました。これまでにない規模です。これ、九百九十四件の死亡認定があったということなんだけれども、情報不足等による評価不能とされたものが、うち九九%ということになっております。これ、市販後の安全確保対策、安全対策が確保されると言えるのかと、言い難いと思うんですね。そういう意味でも、踏み出す規制を緩和するところが極めてリスクは高いんだということを指摘したいと思います。
次に、要指導医薬品の販売見直しについて確認をしたいと思います。
医療用医薬品から市販向けに転用されたばかりの要指導医薬品については対面販売、これが義務化されてきました。その理由は何かということを確認。現状でどれだけ対面販売の実施ができているのか二三年度に調査されているということです。その結果も御紹介ください。
○政府参考人(城克文君) まず、理由でございますが、要指導医薬品につきましては、これは、初めて一般に市販される医薬品でありますこと、そして広範に使用された場合に健康被害等の発生を低減させるための方策が明確になっていないことから保健衛生上のリスク評価が確定していない医薬品と位置付けられること、一定の調査を経て一般用医薬品に移行するものであり、調査期間内において最大限の情報を収集した上で適切な指導を行う必要があることということから、こういったことを踏まえまして、薬剤師が対面で指導、情報提供等を行った上での販売が必要とされてきたものでございます。
実態でございますが、現行の医薬品の販売ルールの遵守状況につきましては、実際の医薬品販売の状況を調査し実態を把握することを目的として医薬品販売制度実態把握調査を実施しております。二〇二三年度の調査結果におきましては、調査対象のウェブサイトにおいて要指導医薬品の取扱いはなかったこと。要指導医薬品の販売時における使用者の状況確認については調査対象の九六・一%の薬局又は店舗販売業で行われていたこと、要指導医薬品販売時における文書を用いた情報提供については調査対象の九一・〇%で行われていたこと等を公表しているところでございます。
○倉林明子君 一般医薬品第一類ということでいうと、その実態調査ですけれども、店舗で情報提供されていない割合、これ二割ということじゃないですか。さらに、インターネット販売では対応者らが薬剤師でない場合、これも二割あったということが、今あったかどうか、紹介あったかどうかですので、確認をさせていただきたいと思います。
で、これ健康被害の可能性もあるということで義務付けしているんだけれども、こうした実態もあるわけです。現行法令の、法制の遵守徹底こそ私は求められているというふうに申し上げたい。
今回、法案では、要指導医薬品であっても、薬剤師によるオンラインでの服薬指導を受ければネットでの販売が可能となるだけでなくって、さらに一般用医薬品については、コンビニに薬剤師がいなくとも条件を満たせば購入が可能となるということになります。薬剤師の指導を受けた確認証を示して購入を求める顧客が来た場合、質問を受けるということも想定されると思うんですね、その場で。で、対応するのは無資格者という現場の想定もできるんですけれども、そういう場合、無資格者の受け答えというのは、医師法、薬剤師法、これに抵触しかねないというふうに思うんですけれども、いかがですか。
○政府参考人(城克文君) お答え申し上げます。
今般の改正法案におきましては、必要な専門家の関与を確保しつつ、デジタル技術の活用により医薬品のアクセス向上を図るため、専門家が配置されている薬局や店舗販売業がデジタル技術の活用により、遠隔での管理を行っていることを前提に、専門家のいない店舗において一般用医薬品の受渡しのみ可能とする新たな枠組みを設けることを盛り込んでいるところでございます。
この遠隔による一般用医薬品の販売に当たりましては、購入希望者に対しまして薬局や店舗販売業の薬剤師等がオンライン等により販売時の情報提供や相談時の対応等、一連のやり取りを経た上で販売するということを想定しております。受渡しのみを行う店舗の無資格者が医薬品に係る質問や相談に応じることは想定をしておりません。
今後、受渡し店舗での医薬品の受取の際に購入者が相談対応を望む場合を想定した要件等も含めまして、関係者の意見や実施状況等も踏まえて検討し、具体については指針を策定してお示ししていきたいと考えております。
指針の作成におきましては、遠隔での管理を可能とする本制度の特徴も踏まえまして、具体的な事項について検討しますとともに、それらに基づく監視、指導も徹底をしてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 規定は、法案の中では想定していないけれども、今後はガイドラインも作っていく必要があるということは想定されるんですよ、そういうことが。そういう、現場際でそういうことも想定されるので、私は、違反、これ禁止するということになるとしても、無資格者がそういうことをやってはいけないよということになっていたとしても、リスク高まるということは指摘しておきたいと思うんです。
で、法案は、乱用のおそれのある医薬品について規制の強化が盛り込まれているわけですけれども、薬剤師の対面販売の規制緩和もあるわけで、これは乱用を助長しかねないと。オーバードーズの問題が焦点にもなっておりますけれども、乱用の助長にもつながりかねないと思いますが、いかがか。
○政府参考人(城克文君) 今般の改正法案におきましては、先ほど申し上げましたように、必要な専門家の関与を確保しつつ、デジタル技術の活用によりまして医薬品へのアクセス向上を図るためにこのような規制、制度改正を盛り込んでおるところでございます。
その上で、市販品の乱用対策につきましては、乱用のおそれのある医薬品を指定濫用防止対策医薬品と位置付けまして、年齢や購入数量に応じた対面やビデオ通話による専門家とのやり取りや、頻回購入対策への対応などを求める制度改正を盛り込んでおりまして、乱用防止の観点から必要な対策も同時に行うものでございます。
この制度の施行に向けましては、この指定濫用防止医薬品の販売を含めまして、法令上の遵守事項など必要な留意事項等を具体的に示した指針を作成をすることとしておりまして、関係者とも協議の上、具体的に示してまいりたいと考えております。
また、実効性確保のために行政が適切に遵守状況を監視することもこれは重要でございますので、薬事監視の適切な実施方策につきましても、実施主体であります都道府県等と十分に協議をしながら検討を進めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 やっぱり、一般医療薬品においても薬剤師による対面販売、これきっちり担保していくということが私、必要だと思っているし、薬剤師の対面販売に限定していくべきではないかと、基本としては、規制強化の方向としては。いかがでしょうか、最後。
○国務大臣(福岡資麿君) 若年者中心とした市販薬の過剰服用、いわゆるオーバードーズが社会問題化しておりまして、政府全体として孤独・孤立対策も含めた様々な対応を進めている中で、医薬品の販売制度においても見直しを行うこととしておりますが、一方で、セルフメディケーション推進等の観点から、専門家の適切な関与を前提とした上で、医薬品のアクセスの確保も重要だと考えています。
このため、本法案では、指定濫用防止医薬品のインターネットを介した販売において、大人への少量の販売については、必要な情報提供等について義務化の上、これまでと同様の方法でのインターネットでの販売を可能といたしますが、一方で、若年者への多量購入については対面、インターネット販売問わず禁止とするほか、若年者の少量の販売であったり大人の多量購入等のリスクの高い購入時にはビデオ通話による薬剤師等の専門家と購入者のやり取りを義務付けることとしておりまして、保健衛生上必要かつ医薬品へのアクセスにも配慮した合理的な対応をさせていただいていると考えております。
○倉林明子君 先ほど薬剤師の方からも指摘があったように、なかなか防げないですよ、オーバードーズの問題は。そういう意味でいうと、医薬品の安全性、有効性、これ確保、これ後退につながりかねない大きな改正になっているということを指摘して、終わります。