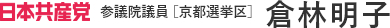高齢者の労災リスク減らせ 労働安全衛生法改定案(2025/4/10 厚生労働委員会)
(議事録は後日更新いたします)
労働安全衛生法改定案が10日の参院厚生労働委員会で自民党、立憲民主党などの賛成多数で可決されました。日本共産党とれいわ新選組は反対しました。日本共産党の倉林明子議員は質疑で、化学物質による健康障害防止対策と高齢者の労働災害防止についてただしました。
化学物質の管理・規制方法が、個別の物質の規制からリスクアセスメントに転換されたことをうけ、改定案では、危険・有害情報の表示及び通知が事業主に罰則付きで義務付けられます。倉林氏は、リスクアセスメントの実効性を高めるために「公的機関の専門性の向上と体制強化なしに、労働者の健康確保にはつながらない」として労働行政の体制強化を求めました。
また、倉林氏は、高年齢労働者の労災防止措置を事業主の努力義務とすることは当然の措置と指摘。60~65歳の雇用確保措置について、事実上退職を強いられる、勤務日を減らされる、賃金が最低賃金など極端な収入源となる実態があると指摘。「こうした実態でも違法とならないことから、生活に必要な収入を確保するために、慣れない仕事への再就職、ダブルワークなどの長時間労働を招き、結果として、高齢者の労災リスクが高くなっているという認識はあるか」とただしました。
福岡資麿厚生労働相は「(働く高齢者の特性に配慮した)エイジフレンドリー指針を通じて働く高齢者の安全と健康を守る」などと答弁。倉林氏は「安定した雇用継続を担保してこそ労災リスクを減らせる」と強調しました。
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。
化学物質による健康障害防止対策についてまず伺います。
化学物質の管理規制方法が物質ごとの規制からリスクアセスメントに転換され、国際基準であるGHS分類によって危険性、有害性が確認された対象物、リスクアセスメントの対象物、これがこれまでの約三百物質から令和八年四月には二千九百物質ということで、およそ十倍に対象が拡大されることとなるわけです。
そもそもこのリスクアセスメントというのはどういうものなのか、簡潔に御説明をいただきたい。
○政府参考人(井内努君) 労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。
リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討するものであり、事業者は、その結果に基づき、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずる必要があるというものでございます。
○倉林明子君 つまり、このリスクアセスメントが確実に実行されると、これがあってこそ、労働者が吸入する有害物質の濃度を把握する、暴露限界値以下に管理すると、こういうことができるようになるわけですよね。そこまでつながって初めて労働者の健康確保というのが可能になるというものだと思うわけです。
ところが、検討会の報告書によりますと、二〇一七年の実施率は五三%、若干その後改善されているかと思いますけれども、その時点での実施率が低いという、五三%にとどまっているという状況の理由は何か、上位二番目までの理由と、それが全体に占める割合はどうなっているのか、そして、実施率向上させないといけないというのは当然だと思いますけれども、そのためにどんな取組をされているのか、全部でなくて結構ですので、主なものをお願いします。
○政府参考人(井内努君) 平成二十九年労働安全衛生調査の特別集計によれば、事業者がリスクアセスメントを実施しない理由については、人材がいないが最多で五五%、次いで、方法が分からないが約三五%となっております。これは、取り組んでいないといった回答をしたところの内訳でございます。
これらの課題に対応するため、厚生労働省では、業種別、作業別マニュアル、保護具の選定マニュアルを作成していること、リスクアセスメントを担う化学物質管理者の育成のための講習を実施していること、化学物質に関する疑問や質問に電話やメールで相談に応じる相談窓口の設置をしていること、保護具の使用方法等を解説した動画教材やQアンドAを公表、リスクアセスメントの実施体験ができるワークショップ型のリスクコミュニケーションを実施している等の支援を実施しております。
○倉林明子君 紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。
そうすると、リスクアセスメントはできるということになっても、リスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。
評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。
今回の法改正によって、対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小企業にとって大きな負担になるというだけじゃなくて、新たに危険有害性情報の表示及び通知には罰則もこれ新設されるということになるわけです。実効性をどう高めていくのかということについていえば、民間の専門家の育成にとどまらず、やっぱり公的部門での抜本的な体制の強化が求められると思います。これだけ増やすんですから、対象も。
監督署、労働局、労働安全衛生総合研究所、これ、それぞれどう体制をこの法改正に伴って強化するのか、お答えいただきたい。
○国務大臣(福岡資麿君) 危険有害な化学物質等の通知を受け取った事業者が行いますリスクアセスメントは、労働安全衛生法に基づく事業者の義務でございまして、適切に行われていなかった場合には労働基準監督署が指導を行い、是正を求めることになります。
また、リスクアセスメントに関して十分な知識を持たない事業者もありますことから、都道府県労働局であったり労働基準監督署では、業界団体を集めた集団指導や説明会、個別事業場に対する助言にも取り組ませていただいております。
また、独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織でございます労働安全衛生総合研究所では、専門家が化学物質の有害性の調査等を行うことによりましてリスクアセスメント対象物質の追加につなげるなど、最新の科学的知見に基づいた制度の改善に寄与しているところでございます。
今回の法改正等によりまして、化学物質に係る各種取組はますます重要となってきますことから、今後とも、化学物質対策の円滑な施行のために必要な体制の確保に努めながら、リスクアセスメントが的確に実施されるような取組を進めてまいりたいと思います。
○倉林明子君 だから、最後のところの中身を聞きたかったんですよ。必要な体制は確保すると、じゃ、必要な体制をどのように見積もっているのかということなんですよ。
もう一回答えられますか。
○政府参考人(岸本武史君) お答えいたします。
必要な体制確保につきましては、毎年度必要な定員要求について根拠を添えて当局と協議をしているところでございまして、これについては、今後の改正がなされました場合には、円滑な施行ができるような体制確保について、大臣の御指導もいただきながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。
○倉林明子君 今、三百が対象物質二千九百に拡大していると。そして、現場際では今の三百でも十分な対策どころか、人がいないとか方法分からないということでできていないと。現状がそこからのスタート、この法改正でね、持っていかないけないということですから、本当に必要な体制がいかにあるべきかということは本気でこれやっていただくと、健康守ると、労働者の健康守るという観点から、被害や障害起こってからでは駄目だと、防止対策としての強化求められるということ強調したい。公的機関の専門性の向上、さらに体制強化、これ抜本的に強めていただくこと抜きに労働者の健康確保にはつながっていかないと厳しく指摘をしておきたいと思います。
そこで、高齢者についても私も質問したいと思います。
高年齢労働者の特性に配慮した作業環境の改善、そして作業管理その他の必要な措置を講ずるって、これは、高年齢労働者が増えて、増加、そして労災事故も増えている、当然のことだと思っております。努力義務にとどまっているけれども、改正必要だと思います。
そこで、一方、高年齢者の働き方はどうなっているかということで申し上げますと、六十歳以上で多様な働き方、これが本当に拡大しております。高年齢者雇用安定法、これによって、事業主には六十歳から六十五歳までの雇用確保措置がこれ義務付けになっているんですよね。
ところが、実際の現場でどんな雇用継続が実施されているかということでいいますと、これ大企業ですよ、電機大手のところでは、定年は六十歳として変更せずに、会社は遠隔地異動を含む仕事の選択や、社内で仕事が見付からないということだったら定年退職を選ばざるを得ないというような選択肢を提示するんですね。さらに、あるいは派遣会社か退職か、二択だと、こういう迫り方もしています。事実上、労働者には退職を強いるというような制度になっているという現状をお聞きしております。
この継続雇用で、他の例ですけれども、あっ、電機大手でほかの例ですが、週五日の労働を労働者は希望していると、ところが用意できる条件は週に一日、二日、三日と、こういうようなケースあるんだということですよね。六十五歳まで年金出ませんから、そういう意味でいうと、賃金は最低賃金という条件も示されております。
こういった低賃金の働かせ方、あるいは退職を迫ると、こんなことが大企業で横行しているんですよ。こんな働かせ方に私は問題、継続した雇用の確保ということで継続雇用制度の下でやっているんだけれども、こんな働かせ方に問題ないのかということを聞きたいと思います。
○国務大臣(福岡資麿君) 六十歳以上の雇用確保措置につきましては、企業に対しまして、定年の引上げや継続雇用制度の導入等によりまして六十五歳までの雇用機会を確保する制度の導入を義務付けているものでございます。
定年後の継続雇用制度における労働条件につきましては、各企業におきまして、高年齢者雇用安定法を始めとする雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で労使間で個別に決定されるものでございます。
個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、高年齢者雇用安定法につきましては、法律に基づく指針において高年齢者の就業の実態や生活の安定等を考慮した適切なものとなるよう努めること等を示し、企業において留意していただくように啓発指導に取り組んでおります。
今後とも、こういった企業において指針等に沿った対応が取られるよう、ハローワーク等を通じ啓発指導に取り組むとともに、委員御指摘いただきました実態把握等にもしっかり努めてまいりたいと思います。
○倉林明子君 六十歳以上の雇用が事実上継続できないというようなことになっていても、この法上の義務付けでは企業の責任問われないと、違法じゃないと、直ちには、こういうことになるんですよね。
私、こういう実態が広がっているということで、極端に、労働者が六十歳以降、極端な収入減、そして、生活に必要な収入を確保するために慣れない仕事への再就職あるいはダブルワーク、長時間労働を招くということに結果としてつながっているんです。なぜならといったら、晩婚化の中で、六十歳超えたって、大学生、子供さん、抱えているという人も少なくないんですよ。だから、収入必要なのに、こういう雇用継続しか担保されないということになっている。
私、結果として、高齢労働者の労災リスクがこれ高くなっているという状況が一歩広がっているんじゃないかと思うんですけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(福岡資麿君) 継続雇用制度における高齢者の労働条件は、高年齢者雇用安定法の趣旨などを踏まえながら労使間で個別に決定していただくものでございまして、厚生労働省においては、高年齢者雇用安定法及び同法に基づく指針などに沿った対応がなされるよう啓発指導に取り組んでいるところでございます。
この労働安全衛生法においては、労働時間や雇用期間にかかわらず、雇入れ時教育の実施を事業者に義務付けてございまして、エイジフレンドリーガイドラインでは、法律上の義務ではございませんが、高年齢労働者が再雇用や再就職等によりまして経験のない業種であったり業務に従事をされる場合には、特に丁寧な教育訓練を行うことを事業者に対して求めてございまして、これは副業、兼業の形で従事する場合も同様でございます。その上で、危険な作業による災害を防止するための措置であったり、定期健康診断等の健康管理のための措置を事業者に義務付けてございまして、これらを通じて働く高齢者の方々の安全と健康を守っていくというようなことでございます。
今回の法案によりまして、高年齢労働者の労働災害を防止するための措置を講ずることを事業者の努力義務とすることで、より一層の取組を求めてまいりたいと考えております。
○倉林明子君 いや、実際に起こっている事例も紹介して、この雇用の継続制度、雇用確保の継続制度みたいなことをやっている実態というのは、かえって高齢労働者の労災リスクを高くしているんじゃないか、そこには答えていなかったですよ。安定した雇用、これが必要だということを指摘したかったんですよ。
そういう意味で、中小企業で三割超える企業が定年制の廃止、そして定年の引上げ、こういうことで安定した雇用を確保、これは中小企業の方が頑張っているんですよ。大企業ほど貧弱な継続雇用制度にとどまっているという実態があります。安定した雇用継続を担保してこそ労災リスクは減らせるんだという指摘をしまして、終わります。